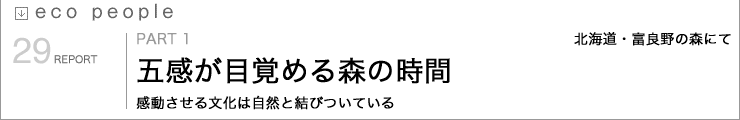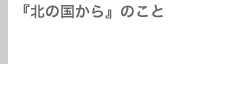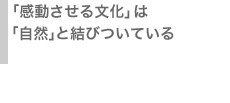倉本聰 Soh Kuramoto
昭和10年東京に生まれる。東京大学文学部美学科卒業。34年ニッポン放送入社。 38年退社後、シナリオ作家として主にテレビに書く。
代表作(テレビ):「前略おふくろ様」/「6羽のかもめ」/「北の国から」/「昨日、悲別で」/「失われた時の流れを」/「優しい時間」「祇園囃子」他
代表作(映画):「冬の華」/「駅」他
著作:「さらば、テレビジョン」/「新テレビ事情」/「北の人名録」/「いつも音楽があった」/「ニングル」/「冬眠の森」/「谷は眠っていた」/「左岸より」/「ゴールの情景」/「愚者の旅」/「富良野風話」/全集「倉本聰コレクション」全30巻他
主な受賞歴:第17回毎日芸術賞/昭和51年度芸芸術選奨文部大臣賞
昭和57年第55回キネマ旬報 第36回毎日映画コンクール
第5回日本アカデミー賞脚本賞
第4回(昭和57)山本有三記念「路傍の石」文学賞
第36回(昭和62)小学館文学賞/ラクシー賞大賞
1996(平成8)モンブラン・デ・ラ・キュルチュール賞
1998(平成10)オメガ・アワードの各国際賞受賞
2000(平成12)紫綬褒章受賞
2002(平成14)菊池寛賞受賞
2002(平成14)向田邦子賞受賞/他