- エコビーイングは未来の世代に健康な地球を伝える環境サイトです。
- エコビーイングとは?
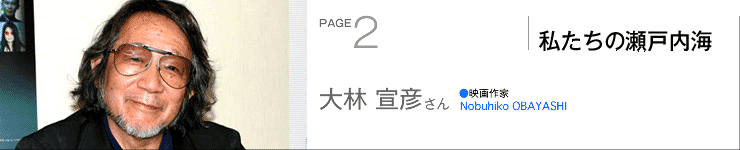
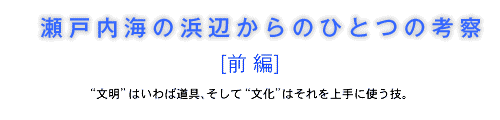 ●
●
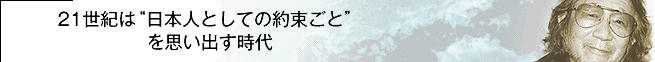 |
||||
 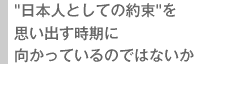 |
僕は瀬戸内海の尾道で生まれ育って、18歳までそこで暮らしてきました、そして大人になってからも“ふるさとは近きにありて、暮らすもの”と考え、尾道を舞台に映画を撮り続けている人間です。死ぬときには“海にぽっかりと小船を浮かべて、裸で太陽を浴びながら、魚を獲って、それをいただいて、波に揺られて死んでいこう“と、ずっと思ってきた人間だったのです。 ところが、21世紀という世紀を迎える頃から、何故か山に好きになってきました。 20世紀に僕が撮った映画のほとんど全てには、海が出てきて、海が出てこないと寂しい思いをしていたのに、21世紀に入ってからというもの、海辺に行ってもキャメラが山の方を向き出したのです。自分で“一体どういうことなんだろう?”と思い、わが家の奥さんと対話をしました。 彼女はプロデューサーでもあり、僕が監督ということもあり、わが家ではよく話し合います。ちなみに彼女は山国の生まれです。彼女は僕と一緒になって始めて、海に出合ったわけで、海についてのこんな考察をしたんです。 「人は同じ海を見ていても、それぞれに“違う明日”を見ている。だから海は誰にでも開かれているし、冒険心を誘うものだ」と。確かに日本人は明治維新以来、海に向って両手を開き、海外のさまざまな文明を受け容れ、世界を広げて来ました。 一方、「山では、人々はばらばらに暮らしていても、ひとつの山を見つめて、手を合わせながら暮らしている。だから、ある種の約束が生まれるのではないか」と彼女は言うんです。「あなたは海に生まれ、きっと海を誇りとして、世界に向って日本を開くべく仕事をしてきたけれど、今まさに、《日本人としての約束事》を思い出そうとして、山を見たくなっているんじゃないの?」と指摘されたのです。 僕は常々、21世紀は、発展、開発という力学に追いかけられてきた20世紀の価値観から脱却し、もう一度僕たちの原点を見つめなおす、“日本人としての約束”を思い出す時期に向っているのではないかと思っています。それはまさに、僕の中のDNAが僕にはっきりと語りかけているんです。 |
|||
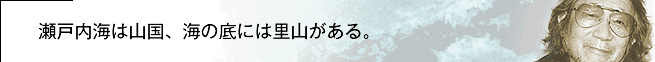 |
||||
 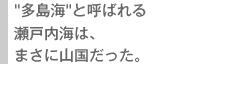 |
その視線を持って瀬戸内海を見つめて、「あっ」と思ったのは“多島海”と呼ばれる瀬戸内海はまさに山国だったという事実です。 ひとつひとつの島のかたちは、まさに山の頂き、山の中腹まで海が上がってきたのが瀬戸内海の島々だということでした。 こうして視点を変えてみると、これまで、きれいで穏やかな海の見えない部分、海の底の景色がはっきりと見えてきたのです。そこには谷があり、川があり、そして様々な生き物の暮しがあったのです。蟹が住む谷や魚たちがわたる川、この情報時代において、見えない海の底にあるさまざまな生き物たちの暮しを、僕たちはすっかり忘れてしまっていたことに気づいたんです。 そして、もういっぺん、瀬戸内海を山国として見直してみると、島々にある鳥居はひとつの約束事を僕たちに“目に見えるかたち”で具現化していました。島の鳥居は、厳島神社の大鳥居と向き合って建っている事実にもやっと気づくことができたんです。 かつて瀬戸内海は、人々の暮しを隔てるものではなく、山から山へと繋ぐ道、“瀬戸内海という大きな道”として、人々の暮しを循環させる大動脈だったのです。 現代は車の時代です。車の文明は“海は道を遮るもの”とみなすようになってしまった。でも本来、それぞれの島に住む人々は、山の暮しを守ってきた里人です。島はそれぞれの里村の象徴です。それぞれの島を良く見つめると、農作物もそこの名産、暮らし方や言葉も違うんです。というのは、日がよく当たる島、日陰になる島、潮の流れが速い島、緩やかな島、それによって、島の文化は微妙に異なるんです。それは、ちょうど山の里村がそれぞれに違うようにね。 瀬戸内海とは、元来、お互いの違いを船に乗って、訪ねて行く海だったんです。そこには“違いを尊み合うという文化”、コミュニケーションの姿があったんです。 ところが20世紀の後半の効率社会に突入すると、“違い”よりは“似たところ”と見つめ合おうという時代になった。しかも“Fast Life”というスピード感を求める時代になった。それはそれでいいんですけど、そのことによって島々の持っていた固有性が失われてしまい、島の文化までもが横並びになってしまった。これは日本全国の故郷に共通して言えることで、僕たちの“日本を失う”行為に組してしまったのです。 今、改めて山を見つめ、ひとつひとつの島を見ていると、そこと交わした約束事を皆が思い出す時期に来たんだ、としみじみ感じるのです。 こんな風に故郷を見直すと、日本はまさに山国であり、海の里なのです。そのどちらかだけとみなしてはいけません。故郷は循環しています。人間の勝手な都合で、循環しているという営みを忘れてしまい、僕たちは故郷の自然から離れてしまったのです。 |
|||
 |
||||
 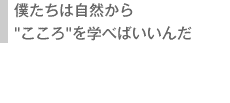 |
今は、“心の時代”だとよく言われます。“もの”や“お金”ではなく“心の時代”になって来たということを、21世紀の到来と共に多くの人々が気づいています。 はっきりと記憶していますが、それは1990年という年でした。僕は日本中のいろんな故郷に講演や映画のロケで行きますが、各地の地方紙では、世論調査の結果が大きく取り上げていました。第一面のトップや社会面に大きく掲載された記事は“物やお金ではなく、心を大切にしたい”というものでした。 80年代、バブルが崩壊するまで、日本人は、“物とお金が豊かになれば、僕たちは幸福になれる”と当たり前のように思っていたんです。ところがあっと気がついて、皆がいっせいに“心の重要性”に気づいたのが1990年だったのです。 よく、1990年代を“失われた10年”と言うようですが、僕に言わせるとまさに“豊かなる10年”です。確かに経済政策において、20世紀的な価値観で言えば、“遅れをとった10年”だったかもしれない。けれど、21世紀になり、人々はあの時よりももっとお金や物を欲しいと思う不況の時代にあっても、“もうそのために誰も心を売り渡さない”という考えが定着していると思います。この10年間は、誠に豊かな10年であったと僕は思います。そういう10年という時間を経て、21世紀を迎えたからこそ、人々は“心の時代”と言うんだと思うのです。 さて、この“心”、“心とは何だろう?”ということになり、これが人々の話題に上っているようです。具体的に心と言うと、人は胸を押さえます。心はHeart=心臓ですが、最近の科学では心は脳が生むものであるということが解明されています。脳の働きが心を醸成するのだということは誰もが既に知っています。この事実を僕たちは知識としては、受け容れることができますが、心が脳というのにはちょっと抵抗があるようです。 古来、シェークスピアを引用するまでもなく、恋する男女は胸をかき抱いて「あなたを好きです」と言うでしょう! 頭を抱えて「あなたを好きです」と言ったら、世界中の恋人は困ったことにみんな頭痛持ちになってしまいますよね。やっぱり心を押さえたい。 胸を、心臓のあたりを押さえたいのではないでしょうか? そこで、改めて“心臓”って何かと考えると、循環のポンプ、体中に血液を送り出し、循環を促す。それで僕たちは健康でいられる重要な器官です。 そこで、もし心の象徴が【喜怒哀楽】であるとしたら、どうでしょう? 【喜】というのはいいですよね。でも、喜んでばかりいると他人の悲しみが分からない自分勝手な人間になりますよね。 そして【怒】、今の時代は怒りたくなることがいっぱいありますし、そして怒らなければいけないこともたくさんあります。でも、怒ってばかりいると頑なになり、心が硬直してしまう。【哀】はそれを知るが上に、他人の悲しみを理解する優しい人間になるでしょうが、哀しんでばかりいると、人間は鋭気を失って滅亡してしまうでしょう。 そして【楽】、楽はいいですね。楽チンで!でも楽ばかりしていると、努力をしない怠け者になってしまう。知恵や工夫を働かせないと人間は馬鹿になってしまう。 【喜怒哀楽】それぞれに大事だけれど、もっと大事なことはその4つがきちんと循環していることで、ひとつところに滞ってしまったのでは、人間は健康ではありません。ここで、「心とは循環するものだ」ということが理解できます。 では、何が一番“心的”であるかと言えば、それは自然です。自然は常に循環している。“心は自然”、心の時代である現在、僕たちは自然から“こころ”を学べばいいんだ、ということがここで見えてきます。 |
|||
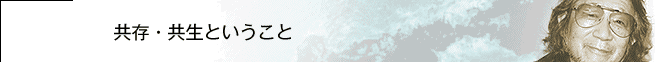 |
||||
 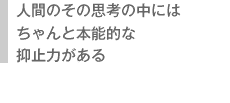 |
さて自然界の循環というのは、ありがたいことであるけれど、厳しいものであって、共存共生とは、全ての生き物がお互いの生命を食べ合うことで、共存・共生しているのです。実に厳しい摂理です。けっして、“仲良しごっこ”じゃない。弱肉強食そのままの世界です。強い生き物はひとり、ふたりの子供を生んで育てれば、種の保存と繁栄が司れますが、弱い生き物は何万という卵を産んで、そのうちのひとつかふたつがやっと育つ。天の知恵である弱肉強食のルールの中であらゆる生命が必死に生き延びているのです。しかも、子孫の繁栄のための務めを終えると、今度は他の生物のための栄養たっぷりの餌となって、その身を循環の摂理に組み込ませていくのが自然界の掟です。 鮭は産卵のため、海から生まれた川を遡り、やっとの思いで産卵を終えるや命絶え、今度は周辺の生き物たち、熊や鳥、その他の多くの生物にその身を捧げて行く。これが共存共生の姿です。 そういう意味で言えば人類もまた、自然の循環の環の中に入って、自分が繁栄するだけでなく、自分の生命が滅びた後は、他の生物のための栄養たっぷりの餌になってあげることを考えなければいけないのではないでしょうか? しかし現実には、人類は今この自然の循環の環から外れちゃっている。つまり、人類は、自然の循環、“こころ”を失ってしまっているのではないか。 人類が再び循環の環の中に入り、また自らの“心”を守るためには、自然界の生物から、その生き方を学ばなければならないと思います。 瀬戸内海の海底に住む様々な魚たちだって、何のために生きているかと言えば、究極は“種の保存と種の繁栄”、そのために生態系を様々に変えつつも生きています。それは、人間もひとつの生命として、なんら変わりはないのです。ただ、人間というのは“裸の猿”と言われているように、弱肉強食の世にいきなり放り出されたら、すぐ滅亡してしまう弱い生物です。ただしそこで、神様の知恵として、仏の願いとして、つまりは自然の意志として、人類は言葉を持った。 他の生き物はおそらく本能的に察知して行っていることを、人間はわざわざ言葉に替え、考え、高めていくということができたのです。そういう意味で、“人間の言葉”が考え、生み出した文明社会というのは、他の動物にとっての鋭い牙であり、厚い毛皮にあたるものです。人類の文明は、それゆえに尊いのです。ただ動物たちは、本能的にツメが伸び過ぎればすり減らします。牙も然り、そして毛皮も一年に一回ちゃんと生え変わります。しかし、人間の知識、科学文明はとめどなく伸びて、尖って、厚くなっていったのです。抑止力のない、行き過ぎた科学文明は人類を滅ぼすと言われています。 20世紀が終わった今、僕たちの科学文明は伸び過ぎた牙、とがり過ぎたツメ、生えすぎた毛皮になって、とんでもなく“へんちくりんな生き物”になってしまったのではないでしょうか? ただ、人間の言葉には文明を生むだけではない、別の能力もある。言葉、そして言語能力、その思考の中にはちゃんと本能的な抑止力があります。 それがまさに文化なんです。 |
|||
 |
||||
 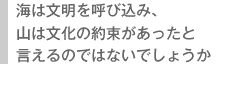 |
文明はいつも“より早く、より新しく、より高く、より効率よく”僕たちの手足に代わって、便利で快適な暮しを作ってくれる。これは素晴らしい道具です。一方、文化は、より古く、より深く、よりゆっくりと、効率は追求せず、不便や我慢はいっぱいあるけれど、それを知恵と工夫で乗り越える。そうすることで、人間は賢くもなる。つまり文明が道具であるなら、文化はそれを抑制しながら上手に使う技のようなものです。20世紀後半は文明ばかりが栄えて、文化を疎かにしてしまった。たから、人類は自らを滅ぼすような危機に面しているのだと思います。 そういう意味では海は文明を呼び込み、山は文化の約束があったと言えるのではないでしょうか?日本は海彦と山彦が共に暮らす、恵まれた国であったはずです。しかしながら、20世紀の後半は海彦になりすぎ、山彦を忘れちゃったという事実を、今、海彦は真剣に考えなければならない。 そして、海彦が約束を思い出すためのひとつのヒントに、島々のてっぺんと見るということがあると思うのです。瀬戸内海を多島海と言って一括りにするのではなく、さまざまな文化を持ち、それぞれの里山の約束の象徴を掲げるひとつひとつの島だという事実に目を向けることです。 急いでいる時は、橋を渡って島を踏み越えてゆくことがあるとしても、時間の余裕がある場合は船で訪ねる楽しみも持つことが重要なのです。 ひとつひとつの島が近づいてくる間に、旅人である自分はこれから会うだろう島の人々と、どのように会話を始めるかということを思い描き、それを楽しむと同時に畏れも抱くような感覚です。ゆっくりと時間をかける旅人のスローライフは大切です。 こんなふたつの選択肢を持ちうることが、文明が発達した社会に住む文化人の賢さではないかと思います。 文明という便利な道具に振り回されて、それを使う“人の心”を失ってしまっていた20世紀、21世紀は、そんな海彦たちがもういっぺん自分の内なる山彦をちゃんと思い出すことが大切なのでしょう。 こんな風に考えていくと、“海の暮し”というのはさらに深くなってきます。 情報の時代と言われますが、情報には科学文明のひとつの弾丸のようなもので、科学文明社会を発達させる強力なパワーがあります。でも、情報は目に見えるものしか見ない。しかし、心は目に見えないのです。むしろ目を閉じた方がよく見える。 |
|||
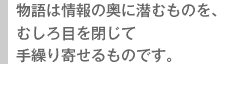 |
“心”とは物語のようなものです。つまり、【喜怒哀楽】も、【喜】【怒】【哀】【楽】がそれぞれひとつひとつの独立したものだと情報ですが、これが循環し出すと物語になります。物語というのは関係性を描くものです。人との関係、【喜】と【怒】の関係、【哀】と【楽】との関係、物語は情報の奥に潜むものを、むしろ目を閉じて手繰り寄せるものです。 ですから海を前にして目を閉じると、海面の下にある無数の生物、豊かな自然が物語として見えてくるのです。 |
|||

|
古来、そういう知恵は海の暮しにはありました。僕が現在暮らしている尾道の向島の海辺、僕はここに30年近く暮らしていますが、まだ娘が小学生のころ、同じ年頃の男の子の友達が出来て、毎日海に行っては、飛び込んで遊んでいました。ところが8月のお盆が来た日から、海辺の男の子は突然、「もう海で泳ぐのはやめた」と言い出したんです、娘にとれば昨日のなんら変わらない明るい海なので理解できない。そこで、「どうして泳がないの?」と聞くと、「お盆が来ると海の底から死んだおじいちゃんとおばあちゃんがやってきて、僕のことが大好きだから、“おいで、おいで”と僕の足をつかんで海の底に引きずりこむんだ。でも僕はまだ生きていたいから“おじいちゃん、おばあちゃんごめんね”と言って、海に行かない代わりにお墓参りに行くんだ。」と答えたそうです。 瀬戸内海の海は一見穏やかな海に見えるけれども、海面から2、3メートル下には冷たい海流が川のように流れています。お盆の頃になると、岸辺にも冷たい海流が入って来て、足が痺れ、おぼれる子供が多いんです。この冷たい、複雑な海流のおかげで、瀬戸内海の小魚は美味しいのですが、瀬戸内海は穏やかなようで、実に生命感に満ちた海でもあるのです。 お盆の頃になるともう海に入らない方がいいことは、現代の子供は科学知識としては知っていますが、それだけでは見た目は昨日の変わらない美しい海で、子供はやっぱり泳ぎたい。そして海に飛び込んで、命を失うような事故が起こるのです。でも、そこで「死んだおじいちゃんが呼ぶ海に行く代わりに、お墓参りに行く」という選択がある。これがまさに文化のある、知恵のある暮しなんです。科学知識だけだったら、お墓参りにはいきません。 そこには、“かつて生きた人の命や、失われたものの遺産や思いの中で自分は生かされているんだ”という意識があります。死んでいった人たちへの敬慕を持つことが、危険から守られ、丈夫に成長できるという賢さが、海の暮しにはかつてあったのです。 これは余談になりますが、ぼくは仕事の関係で日本全国を取材や講演などで旅をします。中でも阪神淡路大震災や九州普賢岳の大噴火の被災地取材では、多くの研究者や復興に携わる技術者たちに直接話しを聞く機会を持ちました。彼らは異口同音に自然の恵みへの感謝と、その自然が時としてもたらす脅威の両面を冷静に享受する姿勢を崩しませんでした。道端の雑草や小さな蟻といえども、自然の輪廻や循環という“界”に帰属し、しっかり貢献している事実を率直に語ってくれたのです。自然に寄り添っている人の視線は謙虚であり、自然界の大きなサイクルを見渡す広い視野で接していました。(後編へ続く) |
|||
後編は監督の“映画論”や故郷“尾道への思い”へと展開されます。 |
||||