- エコビーイングは未来の世代に健康な地球を伝える環境サイトです。
- エコビーイングとは?
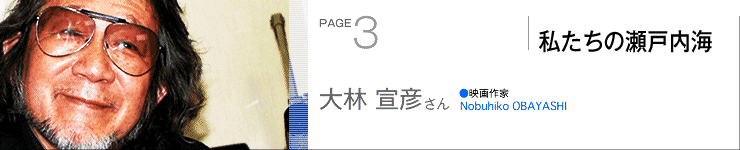
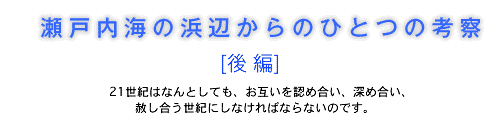 ●
●
 |
||||
 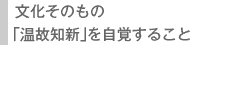 |
文化とは、言ってみれば「故郷自慢」であり、「スローライフ」であり、さらに言えば「温故知新」であるのです。今、「スローライフ」という言葉が生まれているのは、人類の本能が呼びかけているのだと思います。「人類はこのまま行けば滅びるぞ!」という思いが「スローライフ」のような言葉になり、「もっとゆっくり生きようよ」、「古いものを大切にしようよ、そうしないと新しいものは生まれないよ」と語りかけているように思うのです。 僕は人間の本能が言葉を生むのだと思っています。 若者はいつも未来に向って飛び出していくものです。でも、未来とは人類にとって、分からない、予測のつかない、恐ろしいものでもあるのです。でも、その未来に向って飛び出す勇気と知恵が何処から来るかというと、未来と同じくらい長く、深い過去の歴史から学ぶことで湧き出てくるものです。 ロケットだって発射台がしっかりしてしないと飛びません。「温故」とはロケットの発射台のようなものです。そういう意味で子供たちがお年寄りの持つ知恵を継承し、彼らが生きた時代のことをしっかり学び、伝えることは大切なことなのです。そして、何よりもそのことを通して、新しい明日を生きる糧となる知恵や、文化そのもの、「温故知新」を自覚することです。 昨今よく耳にする言葉、「ナンバーワン」より「オンリーワン」だという考え方、これも僕らの本能が言わしめていると思います。 20世紀は競い合って、高め合うという時代だったんですね。これはこれでいいことだと思います。人間がお互いの個性を競いあい、切磋琢磨し、高め合っていく、素晴らしいことです。 でも、人間は愚かにも競い合って、高みに登ろうとすると、フェアに戦うより、ともすると隣にいるライバルを突き落とした方が良い、さらに言えば滅ぼしてしまった方がいいと思うようになるのです。そして、その結果、低め合って、滅ぼし合う戦争を生んでしまった。誰もが「ナンバーワン」になるために20世紀は“戦争の世紀”になってしまったんです。 |
|||
 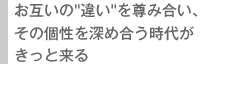 |
21世紀はなんとしても、お互いを認め合い、深め合い、赦し合う世紀にしなければならないのです。お互いの“違い”を尊み合い、その個性を深め合う時代がきっと来るだろうと思っています。 つまり、平和とは“引き分け”なんです。だけどその“引き分け”が“横並びの引き分け”じゃ、元も子もない、さまざまな個性を認め合って、凸凹だらけの人間が等しく生きられるということが、本当の“引き分け”ではないかと思います。 種の保存、種の繁栄ということを考えると、その出発点は男女がお互いに好きになるということです。恋はとても大切なことです。そして世界中の恋人たちはみんな「ナンバーワンの恋人」を持っている。でも、これが本当の意味での「ナンバーワンの恋人」を求め出したら、世界中の男女が「ナンバーワンの恋人」を奪い合って戦争しなければならなくなる。 自然の意思というのは元来、自分だけの「ナンバーワン」を持っているんです。他人にとってどうかではなく、自分自身にとってかけがえのない人、つまりそれは「ナンバーワン」ではなく、「オンリーワン」です。ですから、人類は元々「オンリーワン」、それぞれが「オンリーワン」だからこそ、この世界は循環しているんです。 世界中の全ての生物が百獣の王、ライオンになっても幸せにはなれません。そこには鳥もいれば小動物もいる。微小なアメーバーも生息する、そんな生体系の循環で、共存共生というルールが守られるのです。自然界の共存共生とは、お互いが、お互いの餌として食べられ合うことを前提とする循環です。 「いただきます」は人類の言葉ですが、その意味は「あなたの命をありがとう=Thank you for your life」なのでしょうね。つまり、“相手の命を食すること”であり、“私の命もいつかいただいてくださいね”という環の中に入ることです。 21世紀、人類は今こそ、海から山、山から海への循環の環の中で、自然から多くのものを学びつつ、共存共生という世界に、人間だけが持つ言語を上手に使って、その抑止力を行使して生きていかなければならないと思うのです。 |
|||
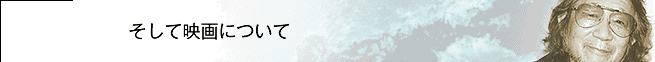 |
||||
 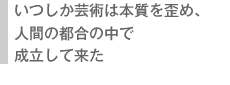 |
僕のように映画を撮ることで、芸術活動を行ってきた人間にとっては、「自然は芸術を模倣する」という言葉に信奉してしまっていた時期があります。 僕は子供の頃、その言葉に感動し、「そうだろうな。自然なんて無意識にそこにあるだけで、芸術は人間の意識によって創られた美しさだ。自然は芸術を真似しているだけだ。だから人間は偉いし、たいしたもんだ」と思い、芸術家になろうと思ったものでした。 でも、あれから一世紀経ってみて、もし、自然が現在の芸術を模倣したら、自然界はすぐ滅びちゃいますよ。芸術は結局、今では人間の都合を表現したもので、芸術も経済や政治の一部に組み込まれてしまい、“売れる”とか、“有名になる”ということが基準になってしまいました。いつしか芸術は本質を歪め、人間の都合の中で成立して来たと思います。 恐ろしいことに、映画も破壊と殺戮を娯楽にして来た歴史があり、その結果として、“2001.9.11”の映像を生み出したと思うのです。僕はあの映像を見たとき、テロリストたちが起した事件のニュースだとは決して思えなかった。あれは、映像芸術の世紀であった20世紀の映像の集大成です。もし、あれがハリウッド映画のラストシーンの一場面だったら、その映画を作った監督は名士になり、製作者は巨万の富を得たでしょう。ということは、ファンもまたそれを喜び、讃えたからです。その罰が当たったのが、あの事件だった。 だからこそ、「芸術が自然を模倣する」。 あの真っ白いスクリーン、画家の真っ白いキャンバス、音楽家の五線譜、小説家の白い原稿用紙、みんな変なものです。この自然界にあんな真っ白い欠落部分はひとつない。何もない空だって、遠くにちぎれ雲があり、星もあり、命も生きているかもしれない。人間だけがあんな真っ白い空白、欠落部分を作ったのです。でも、そこが芸術の原点であり、役割であり、人間の素晴らしさであるとも思うんです。 “この真っ白い空間を、自然の欠落部分を 人間よ、お前の言葉と考える力とで、自然界を再現できるか? 試してごらん“ この空白はまさに人間が試されている場だと思います。僕たちはこの真っ白い空間に、神が創られ、仏が願われたと同じものをあそこに描き出さなければならない。にもかかわらず、自然界が願わない破壊や殺戮を描いて、アカデミー賞を取ったと騒ぎ、金儲けをしていたのが20世紀の芸術だった。そして、2001年9月11日、その天罰が下った。僕はそう受け止めています。 僕たちは真っ白いスクリーンをこの自然界と同じ、ある循環、こころ豊かなもので描かなければならない。 |
|||
 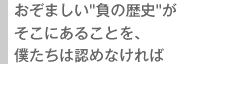 |
たとえば何故僕たちは『STAR WARS』を作ってしまったか?『STAR WARS』を讃えたのか? あの時、選択肢はふたつあったはずです。『STAR WARS』と『STAR PEACE』、そこで何故、『STAR WARS』を選んでしまったのか?やっぱり、おとなしくて地味な平和な映画よりは破壊と殺戮の映画の方が娯楽になるからです。 こう考えてくると、20世紀は科学文明の世紀でもあったけれど、同時に戦争の世紀でした。多くの科学文明は兵器として開発され、経済ですら戦争がある度に発展してきました。おぞましい“負の歴史”がそこにあることを僕たちは認めなければならない。 映画の機材ひとつをとっても、兵器として開発されてきたという歴史があります。たとえば、僕たちが現在使っているカラーフィルムのシステムにしても、太平洋戦争時、空からの攻撃用に、偵察機が敵の陣地を正確に記録してくるため、飛行機に搭載できる小型サイズのキャメラとカラーフィルムがどうしても必要になった。 それまで主に使われていたカラーフィルムのシステムと言えば、赤・青・黄色の3本のネガフィルムが同時にカメラの中で廻っている大型カメラしかなかった。だから、ハリウッドの巨大なスタジオから持ち出すことなんて不可能だったのです。『風と共に去りぬ』の有名なラストシーンのタラの夕焼けにしても、実際の夕焼けを撮ったものではなく、スタジオ・セットの壁に描かれた夕陽の絵を撮影したものです。 ところが戦争になり、軍部からの要請があって、急遽3つの色素を1本に重ねたフィルムが開発されて、ただちにこれが戦場で実用化されたのです。 それは当然、映画製作にも役立って、小型のキャメラのおかげでどこへでもロケが簡単に行けるようになったんです。でも僕たちは、キャメラもカラーフィルムも元々は兵器だったことを忘れてはいけないと思うのです。 “必要は発明の母”と言いますが、それぞれの発明品が誕生するためのDNAがあります。その出発点が他人の命を奪い、陣地を破壊するために発明されたものですから、それらを無自覚に使えば、『STAR PEACE』ではなく、『STAR WARS』を選んじゃう流れが潜んでいるんです。 しかし、ヒューマニズムやファンタジーを描くフィルムが、元々は兵器だったという事実をしっかり知っていれば、それゆえに、平和を願う気持ちがいや増すということも大事なんです。だから僕たちは歴史を学び、【温故知新】の思いを日々新たにしたいのです。コンピューターグラフィックスだって然り、冷戦時代のアメリカの産物、月にロケットを飛ばしてアメリカの国威を世界に喧伝するためのものです。日常的に僕たちが何気なく使っているものの数多くが兵器として開発されたものなんです。だから、経済戦争の論理に合うわけです。そしてその結果、製作された映画が破壊と殺戮を娯楽としてしまうのでしょう。 『STAR WARS』の監督のジョージ・ルーカスが、これと前後するように、当初は全9作の予定を6作で打ち止めにした。「ぼくには違う、作らねばならぬ映画がある」ってね。 僕はそれをきっと『STAR PEACE』だろうと信じているのです。 |
|||
 |
||||
 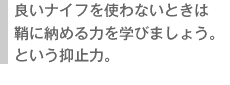 |
科学文明というのはたとえばナイフであって、よく切れるほどいい。 よく切れるから僕たちの手足に代わって、人類に便利や豊かさをもたらしてくれる。でも、文明というナイフを不用意に振り回したら凶器になってしまいます。文化とは“切れれば切れるほど良いナイフを使わない時は鞘に納める力を学びましょう”という抑止力です。 20世紀の僕たちは、ナイフを鞘に納めていると、経済も動かないし、文明も発達しないでいると考えてしまったんですね。抜き身のナイフを振り回した結果、20世紀は戦争の世紀になってしまった。だからこそ、21世紀はさらに切れるようになったナイフを上手に鞘に納める力を学ばないと、行き過ぎた科学は人類自身を滅亡に導きかねない。 では、上手にナイフを鞘に納める術をどのように学べばいいかと言えば、他の生命から学べばいいんです。牙を伸びすぎたら自分でそれを削り、ツメを落とし、毛皮を生え替えらせる動物たちの営みに倣えばいいんです。 地球環境、エコライフというのは、人間が地球のために何が出来るかではなく、実は人間がいかに地球に守られ、生かされているかというかと学び、その上で、どのように賢く地球の生命たちの循環の環の中に入っていくかだと思います。今のままだと、人間は地球にとって、とんでもなく奇妙な生き物になっちゃっているかもしれません。 そのためにも、まず、自分のことを学ぶことが大切なんです。自分のことって、一番分からないものです。でも、あたりを見回せば、いっぱい学ぶべきものがある。そして、僕にとっては、たくさんのことを学ばせてくれる場所のひとつが瀬戸内海なんです。 人間は自分のスケールでしか、ものを体験したり判断したりできません。子供は社会を学ぶために箱庭を作るでしょう?あれを同じで、瀬戸内海というのは小さな場所だから、逆に世界が見えるんです。 日本人が一番グローバルであったのは、なんと鎖国の時代だったと、僕は思います。日本中に他の国があったんです。日本中に様々な文化があり、色んな言葉や色んな幸福感があるということが結果として日本人をグローバルにしていたんです。 明治維新前夜、日本人の侍が世界各国へ行った時、「こんな国際的な紳士がいるのか!」と世界中の人が驚き、尊敬したといいます。当時の日本人はそれほどのグローバルなセンスを持っていた。それが国を開いたとたん、その世界観を失ってしまった。 本当のコミュニケーションとは、自分とは価値観も恋人選びの基準も違う他者が、すぐ隣にいることで、その違いを理解し、深化し、傷つき合っても許し合って、結果として人間をグローバルにするのです。 |
|||
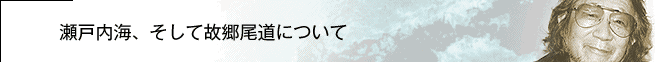 |
||||
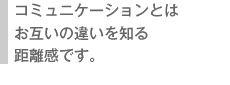
|
そういう意味で瀬戸内海は、子供の僕にとって、隣の島に行くくらい緊張することはなかった。まさにそれは外国に行くことを意味していたんです。 瀬戸内海は、多島海というひとつの文化圏ではないんです。橋が渡りました、ひとつになりました、という横並びの次元のものにしてはいけないんです。 むしろ、違いを楽しみ、尊み合うことを大切にするということが原点にあるのです。 瀬戸内海で上手に生きるということは、グローバルな子供を育てる環境かもしれません。コミュニケーションとはお互いの違いを知る距離感です。 瀬戸内海人はまず、瀬戸内海全体への敬意があります。そして、自分が自分であることを大切にしています。しかも瀬戸内海中を自由に回遊し、止まらない。だから瀬戸内海人にとって、特にお気に入りの場所などないんです。 日本全体を見渡すと、だいたい農村です。農村とは、ひとつの場所に生まれ、育ち、止まり、守り、伝える。 その場所にいる限り、必要な時に雨も降り、風を吹き、日照りもあり、そのバランスがちょっとでも崩れると大変なことが起きるんです。だから都会に出るのも、古来、大志を持つか、石を持て追われるごとき故郷を出て、やがては志を遂げて、故郷に錦を飾るというのが農耕民族の生き方です。つまり“志の社会”なんです。 でも、瀬戸内海は不思議な文化圏で、元々狩猟民族なんです。志ではなく、むしろ心意気です。僕が“故郷は近きにありて、暮らすもの”なんていうのは、まさに瀬戸内海人の発想であって、行ったり来たりが可能なんです。去るわけでも行くわけでもなく、移動に対して全く抵抗感がありません。だから移民が多い地域でもあるんです。瀬戸内海文化圏は日本の多くの文化圏とはやや異なる、つまり海の暮らしが色濃くある場所です。僕自身、日本の山が持っている故郷人の約束を忘れがちな少年だったと思いますし、それについては今も反省もしています。物事にはいつも両面があるものです、良さも悪さもね。 僕の生まれ育った尾道は、山の中腹にあって、太陽がいつも当たる瀬戸内海のテラス、掌のような場所で、外から入って来る異なるものへの受け入れに非常に寛容な場所です。“違い”をおもしろがる、人懐っこい人情がこの街にはあるため、港として発達してきました。尾道人は好奇心旺盛、来るものは拒まずの気風があるんです。ですから、今回の選挙なんかでも、皆で面白がって、驚かないです。 “政治はその土地にゆかりがある者がするものだ”という常識は、あの街には通用しない。だって、皆よそから来たんだ、ということを体験して知っているんです。志賀直哉だって、林芙美子、小津安二郎だって、みんな他所から来たけれど、尾道人は彼らを自分の財産だと思っている、そんな包容力のある街なんです。(おわり) |
|||